本記事は
【Advent Calendar 2024】
7日目の記事です。
🌟🎄
6日目
▶▶ 本記事 ▶▶
8日目
🎅🎁
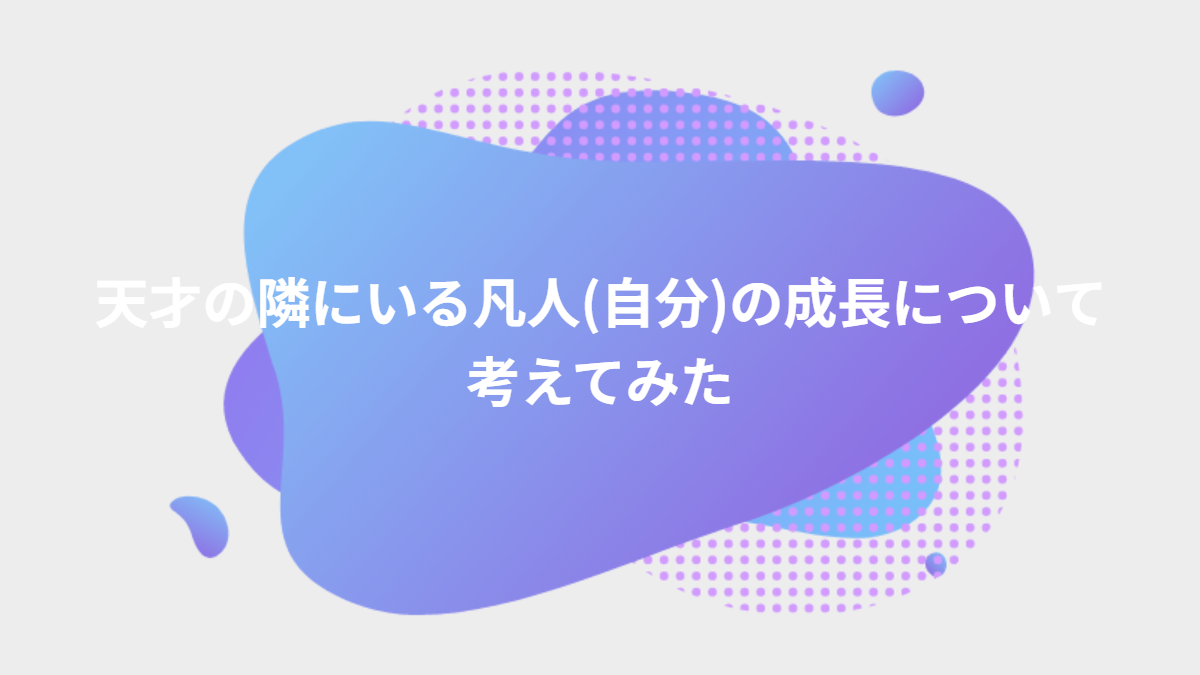
こんにちは、小山です。 寒くなってきましたね、おでんと熱燗であったまりましょう。
今回は、IT業界あるあるのめっちゃすごい人周りに多すぎ問題について、
自他ともに認める凡人の私が大真面目に考えてみた記事です。
この記事で伝えたいことと想定読者
すごいエンジニアが周りにいすぎた結果、
「この業界でやっていけるのかな…」「キャリアこのままで大丈夫かな…」と悩んでいる方を想定しています。
なお「この業界でやっていけるのかな…」は常に私が思ってることでもあります。(爆)
天才と凡人の違い
私の思う天才は以下の特性を持つ人です。
天才の特性(独創性・高速学習・特異な視点)
また、私の周りにいる天才はこのような感じの特徴も併せ持つ人が多いです。
企業の人材もコンテナ化が進んでいるんですかね(?)
- 何かを学習するとき集中ではなく夢中になる
- 環境に依存しないDockerのような安定感
- モチベーションが内発的動機(好奇心や向上心)
では一方で凡人はどんな特性を持つ人でしょうか。
凡人の強み(粘り強さ・協調性・実行力)
そして天才と対比してこのような特徴がある人が多いです。
- 言語化・見える化をして仕事の交通整理が得意
- ↑の特徴から人材育成もできる
もちろん、協調性や粘り強さもまた才能です。
天才と凡人の才能の差は模倣・再現が可能かどうか、という部分で区分しています。
会社にいるすごいアウトプットを出すあの人、
熱量が人の何倍もあるあの人を思い浮かべながら読んでください。
人材と業種についての考え方
社会人になって5年、まだまだルーキー(だと思いたい)私がキャリアに対して出た結論が、
人は以下の3種の人材に区分できるということです。
①どのような環境でも伸びる天才2割
②どのような環境かで伸びしろが決まる人6割
③どのような環境でも伸びない人2割
補足ですが、業種による適性もあることから、
ある職種では③の人材が異業種に行くと①になることもあるという事です。
自分が今いる(就活生の方はこれから入る)業界・業種に対しての適性を正しく知ることが大切です。
自身の経験ですが、私は大学時代は化学を専攻していました。
ただ、授業で言われていることもわからないし実験でも何をやっているのか全くわからず、
気づいたらテスト前に過去問とその回答を覚えるだけの大学生活でした。
きっとこの状態で化学系の職種に就いても③の人材であったと思います。
就職を機にITという業種に挑戦し今は②の人材になれました。(と思いたい)
天才の隣で学んだこと
ではここで天才が隣にいる環境で学べることを共有します。
もちろん世の中には色んな天才がおり、
色んな学びがあると思いますので、みなさんからのコメントお待ちしております。
1.目的意識となぜなぜ分析
ある日のエピソードを共有します。
天才の人は前提から疑います。
日々の業務をこなしているときに右フックのようにこの言葉が飛んできます
「それってなんでそうやってんの?××ってやり方もあるよね?」
そうです、天才の脳内にある膨大なデータベースは非効率を許してくれません。
最短経路が見えているからこその質問でした。
もちろんシステム要件やビジネス要件で、最適解を選ばない場合もあります。
この経験から学んだのは、
(ある程度の知識があるという前提で)根拠を持った意思決定ができているかが大事であり
根拠を持った意思決定は、
目的意識を持った状態でなぜなぜ分析ができることであるということです。
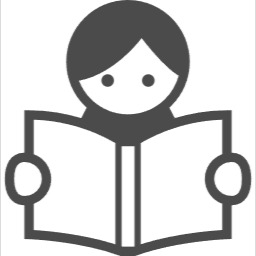
2.モチベーションはブレのないものを
天才の特徴箇所でも書きましたが、
天才は内発的動機づけを持つ方が多く、良い意味で我が道を行く方が多いです。
外発的動機付けが悪いとは言いませんが、外発的動機づけの場合、
個人でコントロールできないものが多く(≒会社の手当や表彰等)、
そこにモチベーションを置いてしまうと、うまくいかなかった時にモチベーションが下がってしまいます。
そのため、なるべくモチベーションはブレのないものを設定するのが良いです。
私は内発的動機づけが難しい場合、マラソンの電柱理論と呼ばれるものを採用しています。
電柱理論とは
マラソンなどで走っていて辛いときに「あの電柱まで走ったら止めよう...」と考え
その電柱に着いたら次の電柱を見て「あの電柱まで走ったら止めよう...」を続けていく考え方です。
そうこうしてるうちにアドレナリンと凝り性のオタク気質が出て楽しくなることが多いです。(経験談)

3.比較するのはサービスと昨日の自分
天才は他人と比較しません。
比較するのは各社のサービスだけです。
余談ですが私の上司(天才)はAWSとGCPを比べてニッコリしています。
そんな上司のブログ一覧はこちらです
内発的動機づけの箇所にも書きましたが、自分の成長や面白いと思ったことをとことん追求します。
他者と比較してそれがモチベーションになるなら良いですが、
私の場合天才と自分を比較してできないことばかりが目に行く性格です。
であればいっそ、他人でなく昨日の自分と比較して自己成長に焦点を合わせる方がモチベーションにつながります。
また自己成長に焦点をあてることで、「今できない事」が「できるようになりたい事」に代わりポジティブな気持ちになります。
これはプロジェクトや実業務においても、天才にも凡人にもそれぞれの役割があるということで、
役割を果たすことで成長や成功が生まれるため、比較でなく違いを楽しむことが大切です。

最後に
みんなちがってみんなすごい、他者へのリスペクトを忘れず明日も元気に働きましょう!(この記事の公開は土曜日)
