本記事は
【Advent Calendar 2024】
3日目の記事です。
🌟🎄
2日目
▶▶ 本記事 ▶▶
4日目
🎅🎁
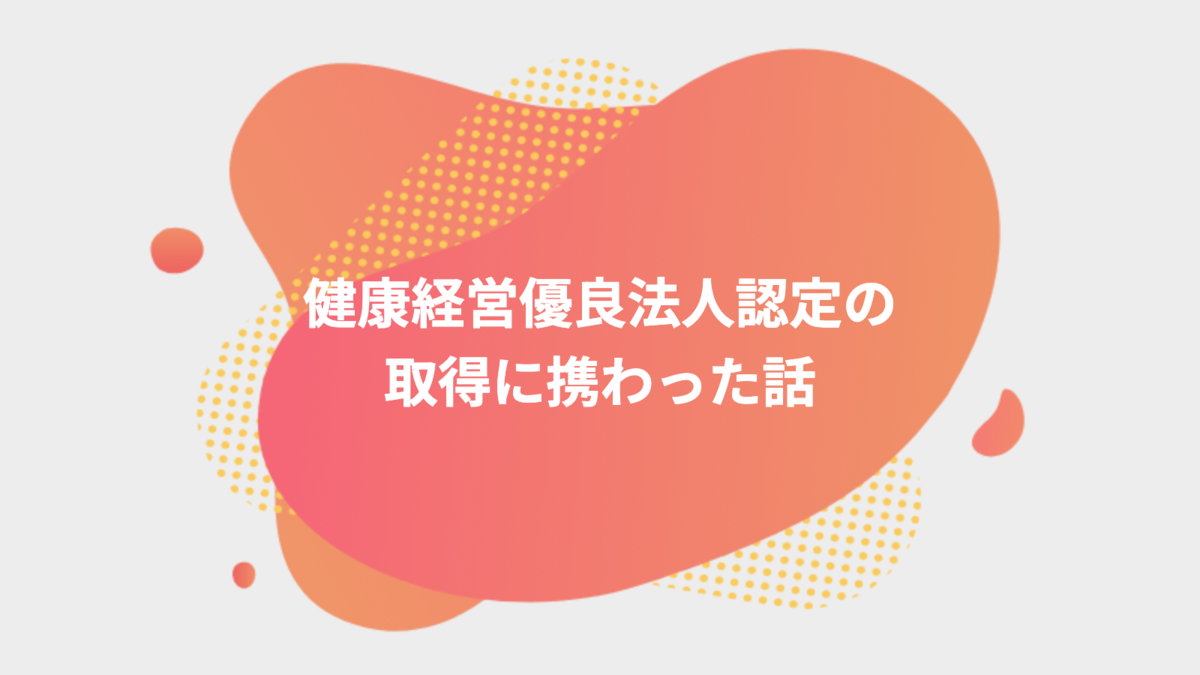
こんにちは。人事部に異動してから1年ちょいが経った中川です。その前は8年半ほど現場で働いていました。
人事部は個人情報を取り扱うようなお仕事が多いため、ブログに書けることがほぼないんですが、今回は異動後から約1年間やってきた「健康経営優良法人認定の取得」について書いてみようかなと思います。
〜はじめに〜
このテーマの内容は、いろいろと記載についての判断が難しい部分があるので、かるーーーーーく触れる程度にしています。
ケンコウケイエイユウリョウホウジンニンテイ……??
この言葉、ずっと言ってると呪文みたいに聞こえるんですよね
さてみなさん、「健康経営」という言葉を聞いたことはありますでしょうか?
わたしは人事に異動するまで「やんわり聞いたことある気がする」くらいでした。
健康経営については、経済産業省がウェブサイトで以下のように記載しています。
「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。
引用:健康経営(METI/経済産業省)
簡単に言うと「従業員の健康のための取り組みは、最終的に会社の利益にもつながるよ」というような考えのもと、健康のための制度整備や施策を行っていくことです。
そして経済産業省が平成28年度に、"優良"な"健康経営"に取り組んでいる"法人"を"認定"する「健康経営優良法人認定制度」をつくり、この認定を受けることで「うちの会社は健康経営に取り組んでますよ」ということを対外的に伝えることができるようになりました。
経済産業省では、健康経営に係る各種顕彰制度として、平成26年度から「健康経営銘柄」の選定を行っており、平成28年度には「健康経営優良法人認定制度」を創設しました。
引用:健康経営とは - ACTION!健康経営|ポータルサイト(健康経営優良法人認定制度)
NRIネットコムもこの認定を受けるためにさまざまな取り組みを行い、2023年から2年連続で「健康経営優良法人」の大規模法人部門で認定をいただいています。 www.nri-net.com
認定を受けることのメリットは?
これはずばり公式サイトにまとまっているので、ぜひ見てみてください。
健康経営のメリット - ACTION!健康経営|ポータルサイト(健康経営優良法人認定制度)
「健康経営に取り組むことで社員の健康状態を改善する」というのは想像がつくかと思いますが、前述のとおり最終的には会社の利益にもつながり、利益率や株価も上がるとされています。
また実際に聞いた話でもありますが、「健康経営優良法人認定を受けている」という点は、昨今の学生さんたちが就職先を選ぶ上での判断材料の1つにもなっているようです。
「認定を受けている企業」と「認定を受けていない企業」が選択肢にあった場合に選んでいただけるよう、認定を受けることは大切です。
ここまで書くと「対外的に印象を良くできるだけでは?」と受け取られてしまうかもしれません。
しかしあくまでも一番のメリットは、認定を受けるための多数の設問に従って社内の施策・制度・環境を整えていくことで、社員がより健康に働くための取り組みを進めることができるという点だと思っています。
やっていること(ふんわり)
設問表は毎年8月ごろに連携され、その設問表に記入して10月上旬に提出するという流れになります。
この設問表が2500行くらいのExcel(!)で提供されており、80問前後の大問とその中に多くの小問や選択肢・記述などがあります。
この内容を一つ一つ確認しながら回答を埋めていくことになります。読むだけで結構な体力を消費します
選択式(1つだけ選択・複数選択いずれもあり)の設問もあれば、具体的な数値などの記入式の設問もあるため、複数選択の回答数を増やしていったり、数値を改善していくことが求められます。
中には「この設問に答えないと認定されませんよ」という設問もあるので、これらを最低限回答したうえで、他の回答状況も踏まえて認定の審査が行われます。
というわけで「その設問とやらはどんな内容なのか」を書きたいところなんですが、具体的な設問内容をどこまで出していいかがわからないので、回答するためにやっていることをふんわりご紹介します。
制度有無の確認
「休暇や費用補助などの制度があるか」という設問がいくつかあります。
制度については「あるかないか」の判断しかできることがないため、「自社の制度として当てはまるものがあれば回答をする」ということになります。
このあたりは他のグループ会社などとも情報連携を行い、どのように回答するかを相談したりもしています。
(制度を一社員がすぐに変えるのはなかなか難しいので、回答を増やしづらい部分です)
研修の実施
「社員や管理職に健康に関する教育を行っているか」という設問が複数あることを受けて、社内で定期的に研修を実施しています。
メンタルヘルスや育児・介護関連など一部は受講率の回答も求められることがあり、社員の受講促進をはかっています。
「受講してよかった!」と思ってもらえるような外部の研修を探して委託したり、探しても見つからない場合は自分で資料や動画を作ったりして、さまざまな研修を実施しています。
健康診断受診の推進
人間ドック・健康診断の受診率や、その後の精密検査の受診率なども回答が必要となります。
このあたりは会社が加入している健康保険組合とも連携を行い、未受診の方には「受診してくださいね」というメールを送ったりしています。
ちなみに私自身の経験談ですが、「人間ドックを受診してみたら病気が見つかった!」ということがあり、早期治療で事なきを得ました。
自分では健康だと思っていても、きちんと毎年診断を受けることで病気が見つかることもあるので、みなさんきちんと毎年受診しましょうね!!!!!
自社サイトへの情報公開
上記の研修の受講率や健康診断受診率などはデータとして外部に開示する必要があるため、NRIネットコムでは以下の企業サイトに掲載しています。
新しい対応の検討
現時点で回答できていないものをどのように回答できる形にするかを検討します。ゼロから考えるものが多かったりするので、正直ここがいちばん大変です。
回答できるものを増やすために、人事のみではなく、他部署や経営層、グループ会社や健康保険組合などに相談したり話を聞いてまわったりします。
他にもいろいろありますが、前回の認定時よりも回答数を増やすべく、日々何かしらの施策を検討しています。
携わってみて思ったこと
認定を受けるためにはやることが山ほどある
個人的に今まで「会社として認定を受けるための取り組み」をほぼしたことがなかったんですが、まず設問数を見て「こんなにやることあるの!?」とびっくりしました。
「今年認定を受けられたから来年も受けられる」とは限らないため、どんどん新しい取り組みを考えて実施して回答数を増やしていかなければいけません。
ただし研修など毎年行わなければならないことも多数あるので、毎年行うことについては定常業務として定着させていかなければと思ってます。
さらに研修などの教育に関する設問が思ったよりも多いため、今はとにかくいろいろな施策に取り組んでいますが、あまりに多すぎると社員の負担となってしまいます。
これからは研修をいくつかまとめて実施するなどして社員の負担を減らしていきたいとも考えています。
関係者がめっちゃいる
「やっていること」の中でも少し触れましたが、健康経営優良法人に認定されるためには人事部だけではどうにもならない設問がたくさんありました。
そこで社内の他部署・経営陣、さらには他のグループ会社や健康保険組合と連携し、より回答数を増やしたり数値を改善していくことが大切だと思いました。
※既に多くの方にご協力いただいております、皆様ありがとうございます!
しっかり理解していなかった制度がいろいろある
設問表に回答していって改めて見返したら、「自社、思ったよりも制度いろいろあるんだなあ」と思いました。
そして「この制度使っておけばよかった」みたいなものもちょこちょこ知るようになりました。
異動してくる前まで存在も知らなかった制度や、「名前は聞いたことあるけどどうやって使うのか知らない」というような制度は知らないともったいないなーと思ったので、社内への周知についても取り組んでいきたいと思っています。
自分の健康を意識するようになった
健康経営に携わり始めてから健康アプリを見てみたんですが、あまりにも自分の健康状態が悪すぎてヒッと強めに息を吸い込みました……
今年度の人間ドックを受診する前に危機感を感じたので、人間ドックに向けてダイエット(というか生活改善)をしました。
朝ラジオ体操、早食いをやめる、階段を使う、帰りに隣の駅まで歩く、Fit Boxingをやる、しっかりお風呂に入る、、、などいろいろな改善をした結果、無事に今年度の人間ドックを目標体重で終えることができました笑
人間ドックが終わってからも上記のことは自然とやる癖がついたようで、健康経営に携わってなければ今頃大変なことになっていたかもしれません。
携わった結果最も得たものは「己の健康意識」でした。ヤッタネ!
〜おわりに〜
ということで、(あまり中身には触れていませんが)健康経営優良法人認定のお話でした。
毎年のことで既に次年度の認定に向けても動き出しているため、引き続きがんばります。
みんな健康であれーーーーッ!!!!!
