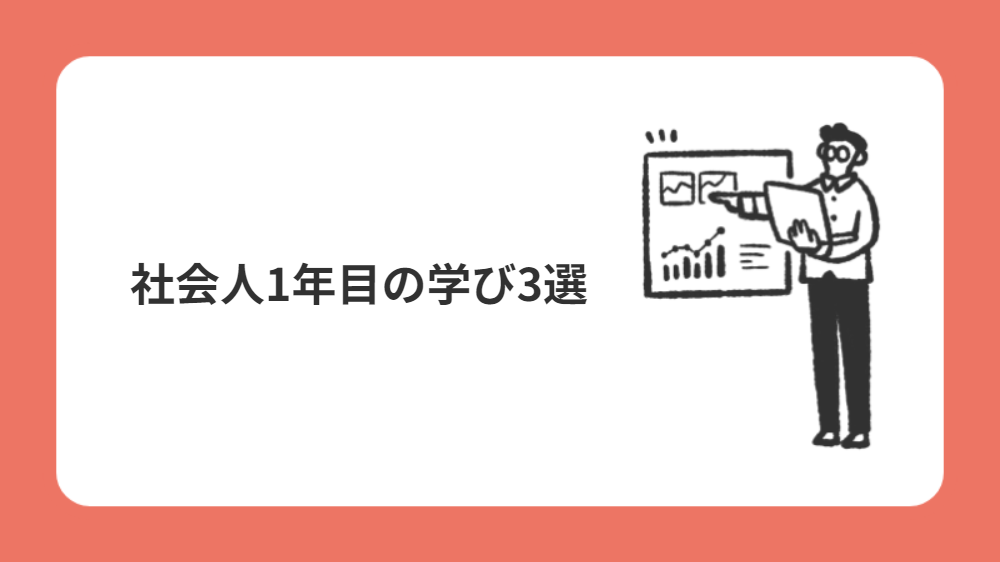
はじめに
初めまして。
「テキトーと適当を使い分ける」がモットーの社会人1年目SEの渡辺です。
ここで言う「テキトー」は大雑把な行為・姿勢、「適当」は文字通り適切な行動を指しています。
やるべきことはやる、手を抜けるところは手を抜くことでこれまでの人生をすり抜けてきました。
そんな私はたまに「テキトーと適当を使い分ける」の「テキトー」が強めに現れすぎてしまうときがあります。
社会人を1年経験して「テキトー」が独り歩きしミスにつながってしまったこと、そこで指摘され得た学びを紹介します。
これから社会人になる方、社会人になることに不安を覚えている方に、失敗してもそこから改善して継続すればなんとかなるということを伝えたいです。
1. 日報には意味がある
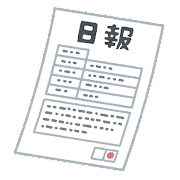 当社では新人は日報を書くというタスクがあります。
当社では新人は日報を書くというタスクがあります。
- 業務内容(何をしたか、何をする予定か)
- 業務時間
- 所感(業務で何を感じたか、学んだか)
- 雑感(思ったことをなんでも記載してよい)
上記4つの観点を記載し、日報を送信します。 私は日報送信に関してミスを犯してしまったので、その時教わったことや日々日報を書いたことで理解した日報の意味を共有させてください。
- 上長が残業時間を考慮し、タスク割り振りを考えることができる
- テレワークが多いため、よいコミュニケーションの場になる
- その日のうちに理解したことなどが間違っている時、上長が指摘できる
- 合っていた場合は、「お、分かってるじゃん」と判断できる
今日やったこと、感じたことを書くという簡単な作業ですが様々な意味があるわけですね。
ではなぜ私が日報の大切さに気付けたのか、上述したミスが大いに関係しています。
配属してから1ヵ月が過ぎたころ、
「渡辺さんの日報が意味をなしていません。インストラクターが見てあげてください」
と指摘を受けました。
それもそのはず、先ほど挙げた日報に記載する4つの観点のうち「雑感」しか記載せずにテキトーに日報を送信していました。
その後、先輩に日報の意味、書き方を改めて教わるという時間をいただき、日報を修正して今に至ります。
日報なんて意味ないじゃんと思っている人に今一度日報の大切さを考えてほしいです。
今回の件を通して、
- 自分のミスは先輩に迷惑をかけることになる
- やるべきことはやる、自分で勝手な判断をすべきでない
- 日報には意味がある
上記3点を改めて実感しました。。
自分のミスが先輩の管理ミスと判断され、自分の代わりに謝っている姿を見て本当に申し訳ない気持ちになりました。
今現在はすべての項目を埋め日報を送信していますが、下記のようにいいことだらけでした。
- 私が理解したと思って書いたことが間違っていた場合、指摘していただける
- 残業時間を見て打ち合わせの日程を再度調整していただける
- 分からないことを嘆いたら返信をいただき問題解消につながる
日報は真面目に書く
教訓です。
2.会議では発言する

- 分からないことはその場で調べる、先輩に聞く(その場で調べることができない場合は、後日調べる or 聞く)
- 質問・発言する
当たり前のことですが会議参加者が実施すべきことですね。
新人のころはまず前提知識(業務知識やIT知識)が不足しているので、なかなか質問・発言しづらいと思います。
ですが理解を深める、認識齟齬を生まないためにも、質問・発言すべきだと思います。
なぜこんな当たり前のことを書いているのか。
そうです。ミスを犯して今の渡辺があります。
配属から2ヵ月くらいが経ったころ新しいチームに参画することになり、その会議に参加していました。
まだまだ知識不足で「この単語は結構頻出だな。あとで調べよう」とメモすることも時折ありましたが、
「今のワードはどういう意味?分からない。まあ今後慣れていくっしょ」
とテキトーな気持ちでいました。
私が発言することなく会議が終わろうとしていたときに、分からないことはその場で質問すべき、と指摘いただきました。
それ以降では、会議に参加して分からないワードがあればすぐ調べる、先輩に聞くことを心がけています。
配属直後、会議している内容はほとんど理解できず、議事録を書こうにも聞き取れないことが多かったのですが、
最近では、ある程度会議の内容についていけて議事録もほぼ自力でとれるようになってきました。
分からないことを解消しつつ、徐々に知識を付けることができている証拠だと思います。
会議に参加したからにはぼーっとせず
分からないことを解消することに努め、発言できるようになりましょう。
3.自分も立派なチームの一員
 配属されたら自分も立派なチームの一員であり、割り当てられたタスクには責任が発生します。
配属されたら自分も立派なチームの一員であり、割り当てられたタスクには責任が発生します。
新人のころはとにかく分からないことが多いため、
「先輩すごいな」「そういう作業をしているんだ」「難しいこと話しているな」
と、どこか他人事のように業務を見てしまうかもしれません。
しかしそれではだめで、
「今後自分がこの業務を実施するのか」
「自分が実施するためにはまずこれを覚えなきゃいけないな」
と、自分事として先輩の行っている業務を見るべきです。
もうお分かりかと思いますが、渡辺またミスをしたからこんなことを話しています。
配属から3ヵ月ほどが経過した頃、リリース作業に立ち会うことになりました。
基本的には、先輩の作業を見て学ぶことが私のタスクでした。
私のチームの作業が一息ついたとき、他チームの方が「〇〇の作業終わりましたか?」と問いかけてきましたが、先輩方には聞こえておらず私だけ聞き取ることができた状況でした。
その作業はすでに終えた認識だったので私は
「終わったみたいです」
と返答したところ、他人事ではないと指摘を受けました。
今後自分が実施するようになるであろう作業のため、注意して見ていたつもりでした。
しかし、確かにどこか他人事としてとらえ、自分事として考えられていなかったがために
「終わったみたい」
と発してしまいました。
自分もチームの一員であるという自覚が足りておらず、自分事として考えられていなかったわけです。
この経験から何をするにも自分事として考え、自分が作業をするときに困らないように、事前に質問・調査をするようになりました。
その成果もあり、今ではリリース作業を一通り実施できるようになりました。
新人の頃から何をする、何を見るにも自分事ととらえて日々の業務に励みましょう。
おわりに
最後までブログを読んでいただきありがとうございました。
これから社会人になる方へお伝えしたいのですが
新人がミスするのは当たり前です。
ミスした後の改善、心構えに重きを置き日々の業務に取り組みましょう。