本記事は
BtoBウィーク
4日目の記事です。
🏢
3日目
▶▶ 本記事 ▶▶
5日目
🏢
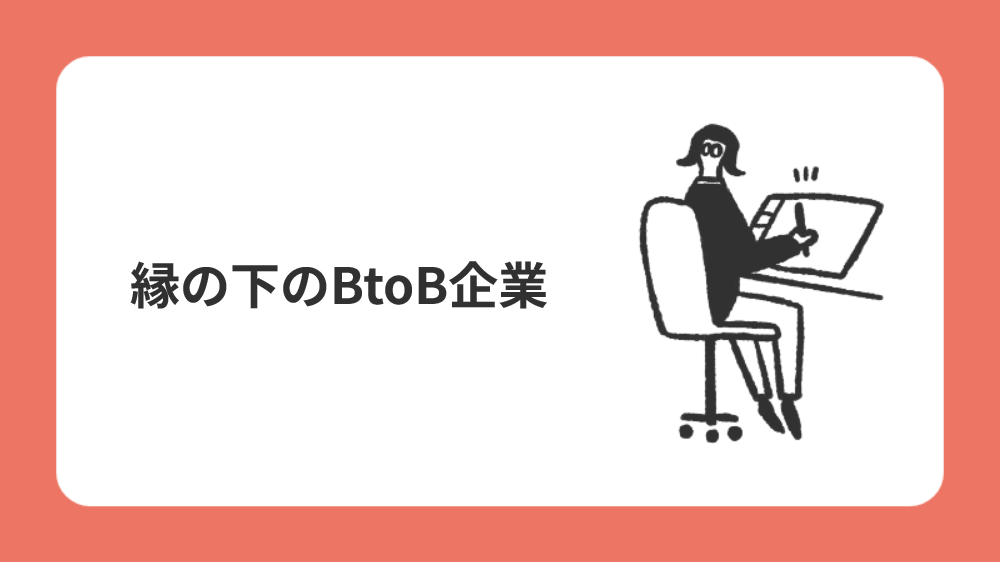
はじめに
こんにちは、NRIネットコム人事部で新卒採用を担当しています、越智です。
2022年に1本記事を書きましたが、そろそろ2本目いっとく?とお声がけいただき、久しぶりに筆を執りました。
※新卒採用担当者、ということで、就活を始めたばかりの学生の皆さんに向けての記事になる予定です。
すでに社会人として活躍されている方には「そんなんわかっとるわい!」という内容かもしれませんがご容赦を。
定番のアイスブレイク
さて、普段の業務として、就活生向けの会社説明会を通じて当社のことを学生の皆さんに紹介するのが私の大きなミッションの一つです。そんな会社説明会の冒頭、私がほぼ必ず投げかけている質問があります。
「”NRIネットコム”という会社名、就活始めるまで聞いたことがなかった人!」
こう問いかけるとほぼ9割の方が手を挙げます。
そう、学生の皆さんは就活を開始するまで、当社のことを知らない方が大半なのです。
おそらく手が挙がらなかった残りの1割の方も、
「うっかり手を挙げるタイミングを逃した」
「みんな手を挙げてるから自分一人くらい挙げなくてもまぁいいかと思った」
というような方がほとんどでしょう。
本当に当社のことを就活開始前から知っていたという方は100人中1人でもいたら多いほうなのでは?というのが私の勝手な目算です。(もし奇跡的に当社のことを知っていた学生さんがいたとしたら、たぶんその人のご家族や知り合いに当社社員がいるのかな?と思ってます。)
当社の知名度の低さに少し悲しくなりつつも、司会からの一方的な会話になりがちな会社説明会で学生の方が確実にアクション出来るアイスブレイクとして活用しています。
しかし、なぜ学生の皆さんは当社のことを知らないのでしょうか?
BtoB企業の宿命
いろいろ理由はあるものの、当社が「BtoB企業だから」というのはかなり大きな要因かもしれません。
事業内容や企業規模、勤務地、福利厚生など、就活中の学生が企業を探す時にキーワードとなる情報はいろいろありますが まず第一のステップとして、「名前を聞いたことがある企業」というのはかなり大きなポイントです。
では学生の皆さんが「名前を聞いたことがある企業」とは?
端的に言うと「消費者にCM/広告を出している企業」=「BtoC企業」です。
BtoC企業は自社サービスや製品・商品を消費者に使ってもらってなんぼ、なわけで。
手っ取り早く認知度&浸透度を上げるためにCM/広告をバンバン出し、その結果としてそのサービスや製品を提供している企業の知名度&浸透度も上がっていきます。
なんかよく聞いたことのある企業だと、例えその会社のサービスや製品を利用したことがなくても、なんとなく安心感も湧きますよね。みんなも知ってるあの企業、みたいな。
そういった企業にエントリーあるいは就職したとして、家族や友達に説明するのも簡単ですね。
「CMでよく見るあの会社」「あれを作ってる会社」この一言で済みます。
また、おそらくお子さんの就活を心配している保護者の方も安心してくれるでしょう。
「安心安全安定」これは常に大事な観点です。
BtoCとBtoB
とは言え、世の中はそんな有名BtoC企業ばかりで成り立っているわけではありません。
BtoCとBtoB、それぞれの規模を示す指標として、こんなデータがあるようです。

2023年8月に経済産業省が発表した「令和4年度 電子商取引に関する市場調査」によると、2022年のBtoCのEC市場規模は約22.7兆円、BtoBのEC市場規模は420.2兆円となっています。
その差はなんと397.5兆円。比率だと約18.5倍もの違いがあるのです。
これはあくまでも「EC市場規模」という一つの指標での比較ですので、決してBtoC市場/BtoB市場の全容がわかるものではありません。
が、企業数やサービス数、全体の売上などといった数字もこれに比例しているだろう、ということは想像に難くないのではないでしょうか。
そしてよほどのゲームチェンジがない限りこの差が覆ることはないでしょう。
「聞いたことがある」からといって市場のマジョリティであるわけではないのです。
決して「マジョリティ=安心安全安定」というわけではありませんが、こういった客観的なデータで見ると、イメージだけで「安心安全安定」と思ってなかったか?別の観点はないか?となりますね。
複数の観点でBtoB/BtoCを就活生向けに解説しているWeb記事などはたくさんありますので、「そういえば改めてきちんと読んだことがないな…」という方はぜひ検索してみてください。
消費者との距離感
さて、就職活動をしている学生の皆さんがBtoC企業にエントリーするきっかけとして、先述した「聞いたことがある安心感」に加えてこういった理由もあるのではないでしょうか。
「消費者(ユーザー)により近いところで仕事をすることができる」
自分が働く企業が提供する商品やサービスが人々の生活をどのように支えているのかが実感しやすく、消費者の反応もダイレクトに受けることができます。
私自身はBtoC企業で働いた経験があるわけではないのですが、社会への貢献度の高さややりがいを感じ、働くモチベーションも高く維持できるのだろうな、と想像します。
- 消費者の声をダイレクトに感じる
- 社会への貢献度がわかりやすい
- 生活に根差した視点を持つことができる
- 多くの人にサービスを提供するやりがいがある
などなど・・・
では、こういった類の働くやりがいはBtoB企業では感じることはできないのか?
私自身の経験で言うと、決してそんなことはありません。
私は2021年に人事部に異動するまで、システム開発を行う部署でシステム開発及び運用を十数年間担当していました。
お客様の基幹システムやそれに付随する各種サービスを開発する部署でしたので、仕事をする際に対峙するのは共に働く社内のチームメンバー、そして社外の顧客(取引先のシステム担当者)が中心です。
しかし、顧客の先には必ずシステムのエンドユーザー、さらに言うと顧客の顧客である消費者がいました。
私自身、直接エンドユーザーの方とやり取りした経験は多くありますし、顧客の業務理解のために、常駐や出向とは違うトレーニーとして顧客の業務を体験し、顧客である消費者と向き合う機会もありました。
同じ部署では顧客とともに消費者を巻き込んでサービスを設計していく、といったプロセスを経て出来上がったサービスもあります。
BtoB企業の多くが、実はBtoC企業を媒体として、BtoBtoCで消費者とつながっている、ということがよく言われます。
特に当社の場合はITというもはや日常生活に欠かせないインフラとなった技術の中で、さらにWebというエンドユーザーに近い部分を得意としていることもあり、消費者とのつながりを実感する機会が比較的多くあるように感じます。
(私は学生の方から提出いただいたESを拝見する機会も多いのですが、「エンドユーザーに近いモノづくりをできる会社だということが説明会から伝わってきた」という内容を書いてくださる方もいらっしゃって、しっかり企業研究してくれているな、と思いながら読んでいます。)
当社に限らず、BtoB企業であっても、実は消費者(ユーザー)に近いところで仕事をすることができる企業はたくさんあります。
もし「消費者に寄り添った働き方をしたい」という理由だけでBtoC企業を選んでいる方がいたら、「それ、実はBtoB企業でもできますよ」と声をかけたいです。
その視点を持つだけで、就活生の選択肢は大きく広がるはずです。
※その代わり、自己分析や業界研究、企業研究がと~~~~っても大切になります。頑張りましょう!
タイトル回収
冒頭で新卒採用担当として説明会で会社を紹介する、というお話をしました。
説明会の中では、当社で活躍する多彩な職種を紹介することがあります。
システムエンジニア、Webディレクター、Webデザイナー、アプリケーションエンジニア、フロントエンドエンジニア、インフラエンジニア、システムアーキテクト、プロジェクトマネージャー...
その中でもインフラエンジニアやクラウドエンジニアといったシステムの基礎となる部分を担う職種を紹介するとき、よく例えとして使う言葉があります。
「システムを支える縁の下の力持ち」
改めて考えると、IT業界のBtoB企業も同じ「縁の下の力持ち」だな、と感じます。
朝、目が覚めてからの行動を考えてみてください。
寝巻から着替えて、朝食を食べて、スマホやテレビでニュースを見て、出かける予定があれば、車やバス、電車も利用するかもしれません。
衣類や食品、メディアによる情報の発信、公共交通サービスといったものはBtoC企業から皆さんが授受する商品、サービスです。
しかし、それらが消費者の手元に届くまでには、BtoB企業が提供している流通や配送システム、また、BtoC企業を支える基幹システムなどが深くかかわっています。
その他にも、コロナ禍の数年で「エッセンシャルワーカー」という言葉が広く知られるようになりましたが、その代表格ともいえる医療現場や地方自治体、公共交通などを支えているのも、BtoB企業が提供する電子カルテシステムや基幹システム、運行管理システムです。
こういった例を挙げていくとおそらくきりがないでしょう。
皆さんが普段CMや広告で見ているBtoC企業の裏には、数多くのBtoB企業が縁の下の力持ちとして活躍しているのです。
おわりに
人が「消費者に寄り添った働き方をしたい」と思うきっかけは、日々の生活の中で受けた何気ない感謝の言葉や、便利/不便を感じた経験など、とても些細なものだと思います。
そんな時、まず一番に目につくのは消費者に直結するBtoC企業かもしれません。
就活を始めたばかりの方は、ぜひそこからもう一歩踏み込んで、かかわっているBtoB企業はどういった会社があるかも見てください。
おそらく業界全体を見渡す視野も広がりますし、ご自分によりフィットした会社を見つけるための選択肢も増えるのではと思います。
ネットコムもその選択肢の中に入っていると幸いです。